
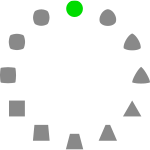

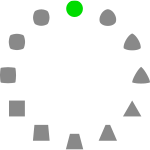


沖眞理さん
と
使って洗って変化した
エプロン
19.03.18
HIROSHIMA
沖眞理さんは、クレイジーステッチと言われる方法論で、縦横無尽に縫い目を生み出し、バッグから小物、洋服までを制作しています。古い布や使い古された布や服を切っては組み合わせ、ミシンを踏んで一体化させていく。毎日ご飯を食べるように毎日縫い物をし、対話するように縫ってきた沖さんの、一針一針に込めるこれまでの時間と思い。
--私につながる家々は女が支えてきた


「これは10年以上前から使ってるエプロンです。綿と麻はガシガシ洗濯していくと質感が変わっていく。それが好きなんです。基本的に長く使ってもらえる物、その人の生活の中で経年劣化していって、その人の空気感も加わるみたいなことが好き。作っておしまいじゃなく、渡してからがスタートみたいな、そういう感覚です」
日傘へとループケアするエプロンを前に、沖さんは自分の物への価値観、ものづくりの哲学をさらっと話し始め、駆け足で自分のこれまでを説明してくれた。
「広島のこの家で生まれて育ちました。23歳までは広島にいて、東京で仕事をしている同級生の人との結婚を機に東京に行き、約20年東京にいました。43歳で離婚してこの家に帰ってきて、今に至ります」

東京は楽しかったが、そもそもは地元を離れる気はなかった。親も親戚も家も好きだった。
「我が家の家系は、女が生活を支える家だったんです。縫い物好きな女が。両親が共働きだったので、学校から帰ると家にいるのはおばあちゃん。おばあちゃんはいつも縁側で何か手を動かしていました。古いセーターを解いて違うものに編み直したり、毛布を座布団にしたり、穴の空いた靴下を補強したり、とにかく何かを縫ったり、編んだりしていました。その色が心に沁みるようないい色だった。でも人形とか飾るようなものは一切作らず、生活で使えるものばかりでした。そのおばあちゃんは父方のこの家のおばあちゃんです。母方のおばあちゃんはミシンの人でした。いま家にある足踏みミシンは戦前からおばあちゃんが使っていたものを今も使っています」。


沖さんは、手縫いとミシンのふたつをそれぞれの家から受け継いでいる。このふたりのおばあちゃんには、それぞれなかなか変わった手のかかる旦那さん、つまりは沖さんのおじいちゃんがいた。母方のおばあちゃんは呉市にいた。
「呉のおじいちゃんは呉服屋の商売をつぶすぐらいお人好しで趣味に生きる人でした。当然女が頑張らんと家がもたない。おばあちゃんの洋裁は生活のためでした。趣味は盆栽、犬のブリーディング、金魚の飼育に朝顔の品評会出品。朝顔の入れる鉢にもこだわって、オリジナルを焼いてもらい、品評会では表彰されたこともあるらしいです。いやあ、おばあちゃん大変だったろうなって(笑)」
なんとも絵に描いたような昔の趣味人だ。
「一方で父方のおじいちゃんは、戦前のアメリカに働きに行って一旗上げたらしいんです。日本に帰ってきてからは、アメリカで一生分働いたと37歳でこの家を建てて、働くことをやめたそうです。子どもは5人いて、おばあちゃん、最後のほうは質屋に通ったと言っていました。そんなおじいちゃんたちでしたけど、それぞれのおばあちゃんから、おじいちゃんたちの悪口を一回も聞いたことないんです。女の人が太かったんでしょうね」


女強しの家系に生まれた沖さんのお母さんも、働きながら沖さんのものによく刺繍をしてくれたという。4歳頃のお出かけバッグがまだ手元に残っていた。忙しく働いていたお母さんは、なかなか寄り添えない分、とにかく沖さんのものばかり作ってくれた。

--暇つぶしと賞金目当て
家族の縫い物仕事を日常の風景としてきた沖さんが、自分の縫い物を始めたのは、東京に行ってから。公民館などでやっている教室に行ってみたが、みんなで同じものを作り続けることに息苦しさを感じて、行くことを辞め自力でやり始めた。
「とにかく自分を満足させるためと暇つぶしのためでした。友だちも親戚もいない東京で溜まっていくストレスを発散するところがなかった。旦那にはこの野郎!と思うことばかりで、一針一針にこの野郎この野郎と思いを込めつつやっていました。4、5年続けて、飽きてきたころに、本屋さんでアメリカのパッチワークの本を見ていたら、布の上に子どもの靴下をべたべた置いてざくざく好きに放題に縫っている作品があったんです。ああ、これよこれ!という感じでした。生地買うお金もなかったし、おばあちゃんも生地を買うことはしてなかった。私も生活感のある生地が好きだし、自分の着なくなった服とか、もらった端切れとかで作ることを3、4年やっていたら、新宿の高層ビル街の中で、ものづくりをする人にひとり1テーブルを無料で貸し出すイベントに声をかけてもらったんです。それまでは公募に出す作品ばかり作っていたので、売り物は何を作ればいいんだろうと。売れなくても自分が使えるように、クレイジーに端切れを縫い合わせたコースターを100枚出しました。そしたらそれが2日で完売したんです。そこでお店の人とも知り合って、2カ月ぐらいしてから、『いま何を作ってるの? 個展してみない?』と言われて、もうびっくり。せっかく声をかけてもらったし、やってみようと。それが30代半ばでした」




アメリカの本にクレイジーキルトというのが載っており、針目が好きだった沖さんを見て、元夫がクレイジーステッチと名付けてくれたそうだ。そしてクレイジーステッチのマークは、29歳の時に産んだ子どもが、小学生の時に沖さんの作風をイメージして書いてくれた。
「私が公募に出していたのは生活のための賞金がほしかったから。取れなかったですが。1人で生きていけるほどじゃないですが、細々と仕事をいただけるようになって、趣味や繋がりができていきました」
そして、43歳で離婚。お父さんが亡くなって1年で離婚し、広島に戻ってきた。
「友だちには『家に呼ばれた』と言っていました。旦那との人間関係がもう繕えないところまできていて、ちょっと気持ち悪い言い方ですけど本当に家に呼ばれた。父が亡くなった分、実家に私一人分の席ができた。ひとりっ子だったので、母といようと」
生前のお父さんに離婚のことを話したら、子どもがいることを理由に大反対されたのだった。お子さんは、今29歳。小学校卒業と同時に一緒に広島に戻り、大学で東京に行ってからは離れたままだ。
--先生が授けてくれた私が唯一縫えるもの

広島に返ってきた沖さんは、20年離れて付き合いのある人も少なくなっていた。ある時、家の近くの洋裁学校に入り、大事な人と出会うことになる。
「おばあちゃんが一人でやっている洋裁学校でした。体育館くらいの大きな建物で、昔はこの辺の人は花嫁修業のために通っていたようです」
45歳を過ぎ、新しく習うには内容が難しかった。でも、沖さんはそのおばあちゃん先生の話を聞くのが好きだった。おばあちゃん先生は犬が大好きで、沖さんが当時飼っていたラブラドールレトリバー2匹を授業に連れてこいと言ったという。もう生徒は10人程度、授業に参加するのは多くて7人くらい。少ないと3人の時もあった。そのおばあちゃん先生は、結婚した1年目にご主人を結核で亡くされ、ご主人の両親と自分が食べていかないといけないと洋裁を習い、習っていたら人に教えるようになり、どんどん広がって地域に洋裁学校を開いた。
「先生からは原爆の時の話も聞きました。被爆した時、お父さんといた先生は爆風で飛ばされ胸にガラスの破片が刺さったお父さんを背負って逃げたそうです。お父さんの胸のガラスが、背負った先生の背中に刺さっていたといいます。そういう経験もあって、女の人が頑張ることをすごく応援してくれる人だったんです。女の人に手に職を付けてほしかった。私が縫い物の仕事をしていることを応援してくれて、学校では最初に私のパンツを縫おうって、パンツの作り方を教えてもらいました。先生は『あんた何を着せてもおっさんぽくなる』と言っていましたけど(笑)」



自分で履くものだけを作っていたが、5年ほど前、グループ展に誘われ、何を出そうかと考え、パンツを出したら、思いがけずたくさん売れることになった。沖さんは、これだと思ったという。
「クレイジーステッチに対して、生地をいろいろと取り合わせるという“お決まりがクレイジー”なもの。お決まりの反対で“リマキオ”としたパンツは布合わせだけで、ステッチ作品と線引きできるにようにクレイジーステッチを使わないものにしました。そのおばあちゃん先生が私のためにデザインして、パターンを取ってくださったパンツを形を変えずそのままずっと作っています」
そのパンツは動きやすくて洗濯しても形が崩れない。おばあちゃん先生は、沖さんが女性らしくなるようにという思いも込めたようだ。先生のパンツはプレーンなもの。そこからクレイジーにしていったのは沖さん。
「クレイジーにはしたけれど、縫う時にはこことここを気を付けてとか、そういう過程を全部覚えています。先生が亡くなられて10年経ちますけど、一本一本いつも対話しながら縫っている感じがします。私が唯一ちゃんと縫えるのはこのパンツだけなんです」

--大好きな先生を送る
「学校に初めて行った時、『ここまで我流でやってきた人は、習いに来ないほうがいいんじゃない?』と先生に言われたんです。悪い意味じゃなくて、そういう言葉で認めてくれる人は初めてでした。我流にやってきたことを認められてうれしかった。とにかくすごく楽しかった。古い校舎に大きな桜の木もあった。生徒は私が一番若いぐらいで、みんな子育ても仕事も終わった70代の大先輩ばっかり。洋裁が全くちんぷんかんぷんの私と先生がいました。先生の周りで過ごしたことで宝物がちょこちょこ、ちょこちょこと増えていきました」

人に教えるため、ずうっと下向いてきた先生の背中は曲がっていた。先生の服は、それに合うように自分でデザインした洋服で、いつもきちっとしていたそうだ。プライドが装いにちゃんと現れている女性で、沖さんもすごく尊敬していたと話す。「尊敬しています、女性として。一人で頑張り通されたことに」
先生は2008年、92歳で亡くなった。旦那さんを早くに亡くしたため、お子さんもおらず学校はすべて更地になった。
「先生が亡くなるまでの約3カ月は集中治療室に入っていたので面会ができなくて、毎日はがきを書いて犬と一緒にポストに入れていました。家族の方が先生に毎日届けてくださっていたんだそうです。先生が亡くなられてご親戚の方から連絡をいただいて、ぜひ犬を連れて仏壇参りに来てくださいって。仏壇まで犬と一緒に入って、犬と一緒にお見送りさせてもらいました」

--縫うことは生きること。
沖さんにとって縫い物は、頭で考えて構図をつくったり、配色を計算したりというものではない。
対象はあくまで自分であり、自分と対話しながら、自分が気持ち良いと思えるところを探していく作業なのだ。
「ここに何を足しても、どれを引いても、それはちょっとなんか気分が悪いというところが完成。それは自分に聞く感覚です。自分に聞いていく日々の中にちょっとずつ変化がある。だから作っていて飽きるということがないんです。毎回の自分に関心があるし、どこまで行けるか、次はどんな物ができるかと考えています。自分の作品に一番興味があるのは私かもしれません。そういう仕事の仕方は楽しい」


沖さんはそうした縫い物仕事をしながら、92歳で認知症でもあるお母さんの介護と高齢でおむつ生活の犬の世話をしている。
「ちょうど今朝まで、介護させられるという気持ちのほうが強かったんですよね。いやいや違う、補い合っとるんだと思い始めました。犬の彼に対しても、母に対してもできないことを私がやる。母からは言葉を掛けてもらったり、犬は近寄ってきたり、私も介護されているような感覚があって、補い合っとるっていうほうが対等で続けやすいかなと、今朝やっとそこまでたどり着きました。ほんまに大変ですね」


沖さんはちょうど還暦で60歳になった。還暦という響きと年齢に落ち込んだという。
「すごいヘビーでびっくりした。なった瞬間から違いました。お勤めしとる同級生は定年で、みんな続けてきたことをやり遂げた区切りがあるのに私は何もないじゃんって。縫い物は続けているけど、続くという言葉は一緒でも、ご飯を食べることを毎日続けてると同じ意味合いでしかないんです」
沖さんにとって縫い物は特別なことというよりも、生きるということと同じところにある。生きることと同じレベルのことがあるというのは、むしろ羨ましいことなのではないか。そして生きるということと同義の行為で縫われたものを手にできるということもまたとても素晴らしい出来事なのではないか。
「ただただ、その時その時の自分と向き合って物はできていくけど、まだ答えは手にしてないだけかもしれませんね。今、60歳から始まるのかもしれません」

--沖眞理さんの日傘が完成しました
沖眞理さんの使って洗って変化したエプロンをループケアし、日傘に仕立て直しました。

聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

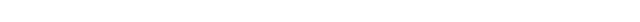

聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

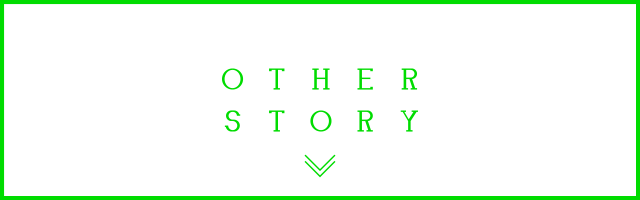
サガワユーイチさんと
伝えることを学んだ
高校のYシャツ
スイーツクリエーター
18.11.22

下田卓夫さんと
お母さんが作った
浴衣
一級建築士事務所ラーバン代表取締役
18.09.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

戸川幸一郎さんと
描いて拭いて汚した
仕事着のパンツ
絵画造形家
18.12.08

竹中真弓さんと
洋裁師の母が残した
生地
キッシュ グラン・ココ 店主
18.08.08

藤島孝臣さんと
沖縄に溶け込むための
泡盛Tシャツ
ガラス工芸家
18.09.28

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18

黒木美佳さんと
seiji kuroki parisの
シャツ
せとうちホールディングス 繊維カンパニー 企画・パターンナー
18.10.28


サガワユーイチさんと
伝えることを学んだ
高校のYシャツ
スイーツクリエーター
18.11.22

下田卓夫さんと
お母さんが作った
浴衣
一級建築士事務所ラーバン代表取締役
18.09.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

戸川幸一郎さんと
描いて拭いて汚した
仕事着のパンツ
絵画造形家
18.12.08

竹中真弓さんと
洋裁師の母が残した
生地
キッシュ グラン・ココ 店主
18.08.08

藤島孝臣さんと
沖縄に溶け込むための
泡盛Tシャツ
ガラス工芸家
18.09.28

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18

黒木美佳さんと
seiji kuroki parisの
シャツ
せとうちホールディングス 繊維カンパニー 企画・パターンナー
18.10.28
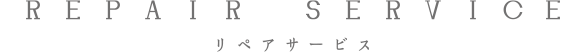
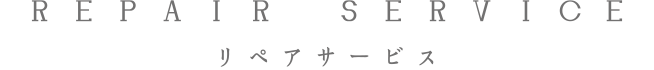
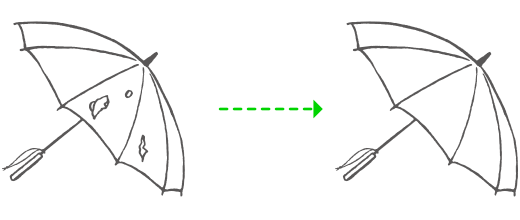
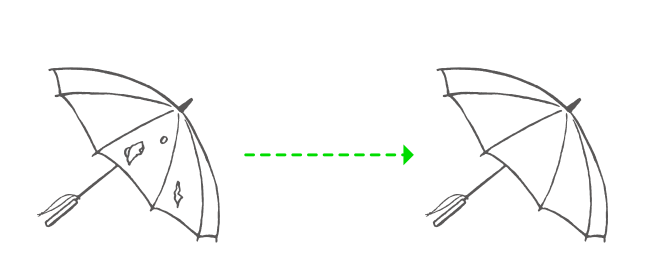
商品毎に、1回分の無料修繕サービス(リペア券)がご利用いただけます。
完成品といっしょにリペア券をお届けいたします。