
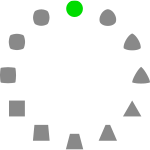

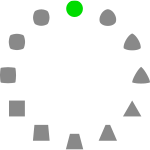


新里カオリさん
と
母親が買ってくれた
ワンピース
19.08.09
HIROSHIMA
帆布の工場に併設されている、立花テキスタイル研究所。「原料も染める材料も自分たちの足元から」という考えのもと、「ゴミ」とレッテルを貼られたもので染色を行い、環境負荷を減らした持続可能な帆布製品つくりを続けている。尾道とは縁も所縁もないところからこの活動を始めた新里カオリさんと、亡くなったお母さんが買ってくれたワンピースのこと。


--『あなたたちきっと尾道好きだから行ってみなさいよ』
「この帆布工場は増築を繰り返し、火事があったりしながら、今年で創業85年になります。元々工場の倉庫だった場所を間借りして立花テキスタイル研究所にしています。高度経済成長期は、この工場にギュウギュウ詰めで働いていたそうです」。
造船業の街尾道の帆布は、船を作る作業員たちの手や頭をやけどから守る手袋や頭巾の製造で賑わってきた。しかし時代は進み、造船業は縮小。帆布工場も足並みを合わせるように減少してきた。新里さんの立花テキスタイル研究所は、常勤は3人と経理、あと縫製として在宅のパートさん3人ほどだという。
「埼玉生まれの私は、もともと尾道にゆかりがあったわけではなく、初めてこっちに来たのは大学院の1年生、22歳のとき。大学の食堂に貼ってあった、アメリカのガラス作家デイル・チフーリという大好きな作家さんの展示ポスターを見て、会場だった広島の現代美術館に行ったときでした。友だちと二人で夜行バスに乗って行ったら、友だちのお母さんから連絡が来て、『あなたたちきっと尾道好きだから行ってみなさいよ』とお薦めされて、おいしいご飯屋さんとか聞きなさいぐらいの感じで知人の女性も紹介してくれたんです」

尾道の帆布を底上げしたいという思いを持っていたその女性は、新里さんが大学でテキスタイルを勉強していることを知り、「ちょっと見せたいものがある」ともう一泊ホテル代を出してくれ、次の日、ある帆布工場に見学に連れて行ってくれた。尾道の帆布が、99%造船業のためのものであり、造船産業が衰退していくことを考えて、バッグをつくっていきたいという相談だった。
--自分たちのやっていることが、社会の一部になってる気がどうしてもしなかった
「一回、東京に帰って考えて、デザイナーの友達を紹介してバッグを作ったりもしたんですが、帆布って絵を描くキャンバスに使うもので、まっさらな帆布は可能性のある生地だと思って、帆布を使った作品制作をするアートインレジデンスをやりたいという企画書を出したんです」


美大生が作品制作をし、すごく高い銀座のギャラリーを借りて発表する。でも来るのは教授と友だちばかりで、ああだこうだ言い合って終わり。自分たちのやっていることが、社会の一部になってる気がどうしてもしなかったという。
「アートってこういうもんじゃないだろうと思ってたとき、目黒区美術館がワークショップをもっと世に広めるべくやっていたプログラムにメンバーとして参加したんです。いろいろな美大の院生たちが何人かでチームを組んで企画するということをやってみて、興味が湧いていました。尾道の空気を感じながら、帆布を使ったら何でもいいという条件で1カ月滞在制作するアートインレジデンスを、結局10年で10回やりました」。
廃校を使って1教室1人ずつ。作品を作って、見てもらっていたが、見にくるのは当然地元の人。はっきりものを言う広島の人から辛辣な意見もたくさんいただいたそうだ。心折れるアーティストもいるなか、新里さんは逆に開き直り、社会にとってアートってこんなもんだよなという気持ちも持てた。
「そういう現実を知る機会でもあり、作品制作のなかで地元の人が野菜を持って来てくれるとか、生活の一部にアートがあることを知ってなおどんなアートを続けていくのかとか、いろんな葛藤を学生のうちにしてほしいなあと思っていました。同時に、帆布のバッグをただ作っていくだけでは話題性が足りない。広報的な役割を担えていけたらとも思って企画していました」
--『もういい加減に住め』

東京で自分の仕事をしながらの10年間。気がついたら年50回は来ていて、交通費も月10万円を超えていました。『もういい加減に住め』という話になったんですが、言われるまで、移住することを想像もしていなかったんですよ」。

そんなに頻繁に来ていてもなお、移住を考えていなかったとは意外だった。
「そもそもは縁もゆかりもないし、まだまだバカンス気分で来てたんです。移住も、すでに知っている人もいて、働くところもあって、家も用意してくれていて、いわゆる移住冒険組では全然ない。そんな保険がかかった上での引っ越しでしたけど、それでも、いざとなったら帰れるぐらいの気持ちじゃないと来れるタイプじゃなかった。新幹線もすぐ飛び乗れる、空港も40分で行けるこの立地だから来れたんだと思います」
--地元のいろんな職種の人に還元する
移住し、製造販売も軌道に乗りはじめた中で、新里さんは次のステップに行きたいなと思っていた。車で島を走っていると、農家が意外とたくさんあり、梅の枝などが切って置いてある。それを染料だと考えるとすごい金額だよなと思い、これどうするんですかと聞いたら全部捨てると。これで帆布を染めたら、この地で生まれた帆布をこの地で育った植物で染めることになり、とても自然なんじゃないかと新里さんは考えた。
「ひたすらどこに使える素材があるかをフィールドワークして、カラーサンプルワークを繰り返しました」



そんな10カ月を過ごし、新里さんはこのプロジェクトを個人活動としてではなく産業として成立させていきたいと考えていた。家具屋さんの家具の木っ端や鉄鋼所の鉄の粉、農家さんの剪定した枝を使い、物づくりで社会的な課題解決をしていきたい。だから、産廃を使うことは第一条件。あとは、外貨を稼いで、地元のいろんな職種の人に還元するという仕組みにしたらおもしろいと思ったという。バッグが売れると、なぜか地元の家具屋や農家にお金が回るようなあり方。産業にすることで、生産能力も上がって単価が下がり、もっと市販のレベルの価格に近づけていくべく新里さんは日々続けている。



--母親と服を選んだのってこの1着だけ
今回ループケアするのは、新里さんが美術大学の受験に合格したとき、お母さんが買ってくれたワンピースだ。

「合格発表が終わって急に、『おめでとう、何が欲しい?』みたいになって、うちの母親はワンピースがすごく好きなんですね。ワンピースばっかり着ていて、じゃあ私もワンピースを買おうかなって。地元の駅ビルで買いました。買ってくれた母は、私が大学院2年生のときに亡くなりました。今の事業のことも当然知らないですし、結婚するとも思ってなかったと思うし、多分心配なまま亡くなっちゃったんですけど。母親と服を選んだのってこの1着だけなんです。大学時代に散々着て、直して直してしながらも着ていました。引っ越しなどを経ても、やっぱり捨てられずにずっと持っていましたね」


お母さんは新里さんが美大に行くことが本当にうれしかったのだろう。
「すごく喜んでくれていました。両親とも教員なんですが、私が美大に向いていると思ってくれたんだと思います。子どもの頃から裁縫や絵を描くなど美大向けの子でした。就職とか、将来の不安も聞かれませんでした。あんまり直接褒めたり、人に自分の子どもの自慢をしたりするタイプじゃなかったんですけど、後で聞いたら、大学受かったときは同僚の人に、『美大に受かった』ってうれしそうだったらしくて、ああ、そう思ってくれてたんだなって」
礼儀などは厳しかったが、進路などについてうるさく言ってくることはなかった。海外にも散々行った。大学卒業後はイタリアの大学への留学も考えていたそうだ。そんなとき、帆布工場と出会った。ちょうど母親が病気になり看病をしなくてはいけなくなった時期、母を理由に留学をやめるのはしたくなかったと思っていた。帆布工場との出会いは運命的だったとも思えてくる。
「反抗期もひどくて、しょっちゅう母親とぶつかっていました。母と娘の関係というのはいろいろあると思うんです。今ぐらいの年になったら分かり合えるところがあると思うんですけど、そういうところまで行けなかったっていう思いがあります。母は貧しい家庭の人だったので、お医者さんになりたかったらしいんですけど、学費が問題で大学に行けず、泣く泣く教員の道を進んだ人なので、自分は夢を叶えられなかったという思いがあったのかもしれません」
--「既婚者トーマス」

新里さんはこの島で出会った男性と結婚している。現在広島大学の大学院で博士課程に在籍しているアメリカ人男性トーマスだ。タブラ奏者のユザーンが、ツイッターで「既婚者トーマス」とつぶやき話題にもなった。英語の先生として日本にやって来るはずが、入れる枠が狭く、試験に落ちて補欠になってしまう。ところが折しも震災の年、外国人たちは仕事をキャンセルし、日本行きを断念する人が多かった。繰り上げで合格し、農業をやるつもりで北海道と四国を第1、第2希望で提出。しかし配属されたのは尾道だった。がっかりしたそうだが、来てみたらすぐに気に入ったという。畑をやりたいらしいから、島で畑付き一軒家があったら紹介してと友人に紹介されたのが、新里さんとの出会い。
大学院での研究は現代日本においても非常に大切なことを対象にしている。
「環境経済学を専攻していて、麻の研究をしています。アメリカの大学で福岡正信さんという、自然農の先駆者を知って感銘を受けたそうです。日本の衣食住を知り、アメリカの単一栽培、連作障害による虫や病気の発生とモンサントなどの関係が嫌だと思うようになった。工業地域のジョージア州出身で、広大なアメリカは手元に農作物が届くまで何日もかかるような状態だったのが、小さな国である日本はフレッシュなものが食べられて四季折々の作物を小さな畑で作っていることがおもしろかったみたいです」

「衣、食、住を切り離してしまったがために、バランスが崩れている。例えば、お米だったら、いまは米粒の部分しかお金にならないけど、昔は藁の部分も草履や家に使われたりしていて、捨てずに全体を使いながら成り立っていたものが、部分的にしか使われなくなった。それを一番体現できるのが麻だと彼は思っていて。麻は、衣服として日本の気候にも一番向いていて、生育も早く、種も食べれて、オイルも取れて石油代わりにもなる。そういうことをトータルで考えたら、麻を復活させることが日本の農業にとって経済的にもぴったりなんじゃないかって。日本で崇拝されて、神社でも使うし、文様も使う。女の子には丈夫に育つように麻子という名前を付けたりもするくらい本当に大切にされているのに、なぜ日本で迫害されるに至ったのかということを一生懸命調べています。時代的にメディカルな方でも徐々に合法化されてきていて、そのうち日本もなるだろうと彼は踏んでいて、そのときにスペシャリストが全くいない現状では相当出遅れてしまうから、自分がいまのうちになっておくという算段みたいですけどね。早く大学教授になれよと思ってます(笑)。早くわたしを食わしてくれ」
博士課程のいま、教授になるのはもうしばらくかかってしまう。立花テキスタイル研究所はこれからどうしていこうと考えているのだろうか。
--『やりたいことを続けるなら、規模を大きくしちゃだめ』

「会社をつくるとき、尊敬してるブランドの社長さんたちが、口をそろえたように『やりたいことを続けるなら、規模を大きくしちゃだめ』と言われたんです。言ってる本人たちのブランドはどこもめちゃくちゃ大きいんですけど。売れるからじゃあ従業員を増やすかとやっていくと、そのうちスタッフを食べさせることが目的になってしまう。本当にやりたいことに年々チャレンジできなくなる。人口減少の日本にあって、大きくすることばかりが正解ではないから、本当にニッチな世界でも、地道にやっていくほうがいいよって言ってくださったので、その言い付けは守ろうかなと思っています」
巨大な造船業とともにあった帆布産業は、これからどんな道をたどり、新里さんが見つける自分サイズはどのくらいになっていくのだろうか。


--新里カオリさんの日傘が完成しました
新里カオリさんの母親が買ってくれたワンピースをループケアし、日傘に仕立て直しました。

聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

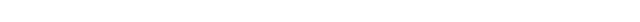

新里カオリ
立花テキスタイル研究所 代表取締役
1975年、埼玉生まれ。
武蔵野美術大学大学院造形研究科テキスタイルコース修了。
2008年、尾道に移住し、株式会社立花テキスタイル研究所を創設。
地元の廃材を使うものづくりと、収益を地元の人に還元するという仕組みは、業界を超えて広く注目されている。
聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

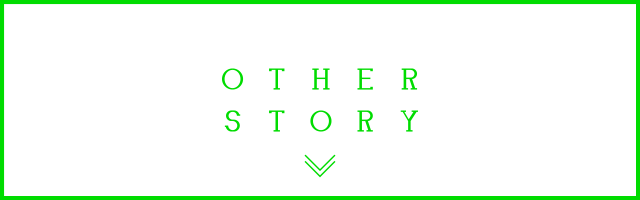
勝矢珠容子さんと
子どもの入学式で着た
絵羽織
株式会社勝矢和裁 会長
19.05.18

友村晋さんと
母親が作ってくれた
顔入りリコーダー袋
株式会社ミジンコ 代表取締役
19.04.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

戸川幸一郎さんと
描いて拭いて汚した
仕事着のパンツ
絵画造形家
18.12.08

杉本拓史さんと
NZ遊学を共に過ごした
フリース
日本料理「野趣 拓」店主
19.02.05

梶原恭平さんと
半面教師の父親の
現場用作業着
広島経済レポート取締役
19.04.29

沖眞理さんと
使って洗って変化した
エプロン
日常を楽しむ人
19.03.18

津金美奈さんと
自分で一式揃えた
成人式の着物
カフェ「kipfel.」店主
19.03.02

藤島孝臣さんと
沖縄に溶け込むための
泡盛Tシャツ
ガラス工芸家
18.09.28

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18


勝矢珠容子さんと
子どもの入学式で着た
絵羽織
株式会社勝矢和裁 会長
19.05.18

友村晋さんと
母親が作ってくれた
顔入りリコーダー袋
株式会社ミジンコ 代表取締役
19.04.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

戸川幸一郎さんと
描いて拭いて汚した
仕事着のパンツ
絵画造形家
18.12.08

杉本拓史さんと
NZ遊学を共に過ごした
フリース
日本料理「野趣 拓」店主
19.02.05

梶原恭平さんと
半面教師の父親の
現場用作業着
広島経済レポート取締役
19.04.29

沖眞理さんと
使って洗って変化した
エプロン
日常を楽しむ人
19.03.18

津金美奈さんと
自分で一式揃えた
成人式の着物
カフェ「kipfel.」店主
19.03.02

藤島孝臣さんと
沖縄に溶け込むための
泡盛Tシャツ
ガラス工芸家
18.09.28

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18
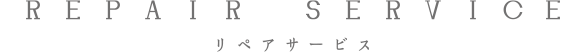
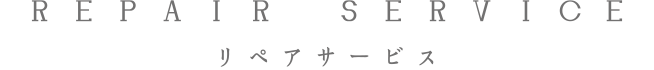
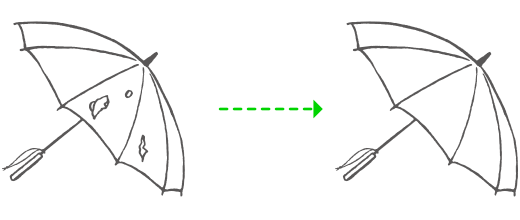
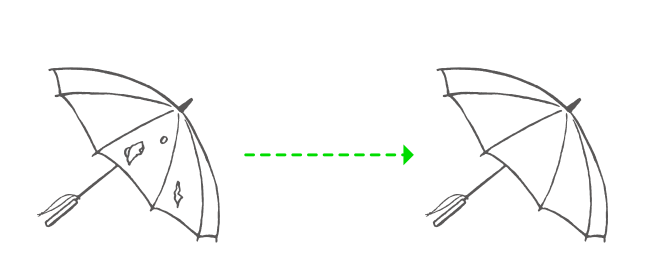
商品毎に、1回分の無料修繕サービス(リペア券)がご利用いただけます。
完成品といっしょにリペア券をお届けいたします。