
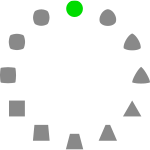

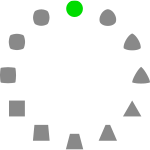


山岸玲音さん
と
勝手に譲り受けた
父のレザージャケット
19.10.28
HIROSHIMA
広島でオペラ歌手として活躍する山岸玲音(れおん)さん。お父さんである声楽家の山岸靖さんに弟子入りし、オペラ歌手を目指したのは26歳のこと。アカデミックな教育を受けず、バンドマンとして活動した後のことだった。声楽家としての父を尊敬し、そのあとを継いでいくという決意をもって活動するオペラの世界とそれまでの道について。
--『人間失格』が呼び覚ました暗黒時代
山岸さんは、東京に生まれ11歳で広島に引っ越してきた。父、山岸靖さんは東京藝術大学の声楽科を卒業し、藝大の講師を勤めていた声楽家。現在は、ひろしま国際オペラスタジオ(HIOS)の全演目の演出を手掛けている。

「88年に父が藝大を辞めることになった時、広島のエリザベト音楽大学から『助教授で来ませんか?』と声が掛かって、『じゃあ、引っ越そう』と。広島の中高に通って、18歳から千葉、20歳で東京に戻りました」
バリトンのオペラ歌手である山岸さんは、元々父親と同じ職業を目指していたわけではなかった。
「子どもの頃は、オペラ歌手になる気はなかったんです。子どもの頃に『ピアノ習う?』と言われて、大した考えもなく、じゃあやろうかなみたいな感じで高校までやっていました。ピアノはとても不真面目な生徒だったのですが、小さい頃から教会の聖歌隊に入って賛美歌を歌っていたり、中高とブラスバンド部に入ってチューバやトロンボーンをやっていたのもあって、譜面は読めるようになっていました。ある時期までは音大に行こうかなという気持ちはあったんです。でもその時は声楽じゃなくてリトミックがやりたかった。高校3年の1学期でもうシフトチェンジして、今度は幼稚園の先生がやりたくなっていました」


親のレールから外れたかったということなのだろうか。
「それもあるかもしれないですね。でも、親はやりたいことをやりなさいと。結果、オペラを志したのが遅くて26歳でした。それまではバンドをやっていたんです。暗いスリーピースバンドでした。90年代の就職氷河期、ニルヴァーナなどのオルタナティヴ・ミュージックが流行り、ニルヴァーナのカート・コバーンが自殺したような頃。太宰治の『人間失格』に18歳で出会い、始めたバンドだったので、暗くダウナーにならざるを得ない感じでした(笑)」
--溢れてくる言葉を書き留める
太宰を始めとした文学に出会った山岸さんはその頃から、ノートに言葉を書き始めた。

「当時は、自分は生きていていいのだろうかという葛藤があって、この気持ちを何とかしないといけない、取りあえずアウトプットしようと書き始めました。同時にいろんな文学と出会って言葉が蓄積されて、言葉が自分の気持ちとリンクした時にバーっと書き始めたら、ノート1冊はあっという間に終わっていました」
特に整理するわけでなく、ただ書き続けノートはどんどん溜まっていった。
「シュールレアリスムに自動記述というのがあってその影響を受けていたのもあります。言葉がたくさん溜まってきて、どうしようと思った時、じゃあ曲にしてみようと。友だちからスリーコードだけ教えてもらって曲を作り始め、数曲できたから、メンバー募集の張り紙を楽器屋に出したんです」
それが22歳。親のレールから外れたいと思いながら、様々な音楽に触れていた山岸さん。音楽に文学という刺激が入り込み、それは楽しみというよりも生きるために必要なものになっていた。貼り紙がきっかけでバンド「UTERO」を結成し、3年半ほど活動したという。
「当時は、コンプレックスが強くあって、自分で自分を脅迫するような感覚でした。文学に出会ってどんどん刺激されちゃったんですよね。だから音に乗せて言葉をとにかく吐くという感じでしたね。とにかく出さないと溺れて死にそうだったんです。ひたすら曲を作ってライブして、出す、出す、出すという毎日。ずっと胃が痛いとか、ギター投げて帰るとか、楽屋で泣くとか、そんな不安定な状態が続きました。ライブハウスの人にも、死ぬなよと言われていました。ディストーションのエフェクターを使うとスイッチが入るんですよね。音と一緒に気持ちもどんどん増幅されちゃってきつくなっていく。みんな口を開けて見ていましたけど、それを3年半ぐらい続け、やり切ったら出すものがなくなってゼロになった」

山岸さんは4年弱のバンド活動で完全にデトックスを終えていた。
「あぁ、これでもういい気がするって。いっぱいいっぱいだったものが本当にゼロになって、精神的な意味で断捨離し切ったんでしょうね。よし、もうやめようって」
音楽で成功したいでも、誰かに伝えたいでも、自分をわかってほしいでもない、ただひたすらに溜まっていたものを吐き出して見事に自己完結していた。
「やり切らないと次のことにコミットできる気がしなかったんですよ」
--河原にひとり立ち、発声練習をした日々

「バンド時代も、親が毎年やっていたHIOSの本公演の手伝いを裏方としてやっていたんです。本番は客席で観ることもあって、自分の両親が演出した舞台が、えらく自分を動かして、感動したんですよ。本公演が終わって東京に帰っても、しばらくその世界から離れられなくて。プレーヤーとして、クリエーターとしてとんでもない人たちに見えた。何年も手伝いをやっていてバンドでもやり切ったし、やるなら今かなと思って、26歳で広島に戻り、親に師事し始めました。いろいろな声楽家や先生を見ましたが、やっぱり父の歌い方が一番好きでした。そこからは修行期間です。自分が東京に住みながら毎年手伝いに帰ってきていた時、母親が『オペラやればいいのに』とぼそっと言ったりしていたんです。冗談っぽくですが。実際始めたら、父は『ようこそ、儲からない世界へ』って言ってくれましたね。本当にそのとおりだなと今になって思います(笑)。でも、26歳からでもオペラを始めた息子を父は喜んでいたみたいです」
HIOSは会員制度のオペラグループで山岸さんが加入した当時で10人ほどのメンバーが在籍していた。そのためすべて手弁当で、出演も裏方も全員でやらなくてはいけなかったという。
「メンバーは基本みんな声楽経験者で、僕のような素人が入ることは珍しい。頭ではノウハウを知っていたんですけど、実際に体を通して実践してこなかったので、発声時の声帯のメカニズムやトレーニング方法を父に教えてもらいながらやりました。ただ僕が手取り足取り教えてもらうというのが嫌なタイプで、ちょっと教えてもらったら後は自分でしばらくやらせてほしいと。河原にひとりで行ってずっと発声練習をしていました。オペラはイタリア語なので譜面を読む作業とイタリア語を理解して覚えていくことを少しづつ。わからないながらにできることを体当たりでやっていました」


エフェクターを使ったノイジーなギターで感情的に言葉を吐き出していた頃とはまったく違う音楽の世界。自分の世界観を守りながらやりたいという思いが、河原での自主練習へと繋がっているのかもしれない。
「修行していたのは、26歳から32歳ぐらいまで。広島市が主催するオペラの全国オーディションの演目がプッチーニの「ラ・ボエーム」だった時があって、それに受かったことで修行期間の第一期を終えた感じでしたね。父親と母親がリアリズムの権化みたいな人たちで、演技、演出でうそっぽいことを絶対やりたくないと。その方法ですごく鍛えられて、自分のポイントだと思ってがんばっていたら、声を掛けてもらえるようになって県外の公演にも出るようになりました。男性歌手が少ないという現実を含め、僕がまだひよっこなのをわかった上で、育てるつもりで目を掛けてくださったんだと思います。だから誰よりも演出家と話ができるようになろうとしたし、スタッフサイドにも自分からどんどんコミュニケーションを取りました。いい舞台が作りたい。リアリティーのあるものをと思って」
--父から受け継ぐもの

両親の元での6年の修行期間を終え、外に羽ばたき始めた。お父さんから見て、息子が一人前になったと感じるのはどんな時なのだろうか。
「父というより伝統芸能の師匠という感じですが、今や同じ目線で話をしています。自分のカラーでがんばっていると見てくれていると思います。父親の弟子はいっぱいいたんですけど、彼のマインドを真に理解できていた人はそんなに多くなかったと思うんです。だから誰より理解している自分がもっと体現していかないといけないとはずっと思っています。自分のキャラクターよりも父がやってきたことはこうで、僕はそれをいいと思ってるからこういうふうに受け継いでいくというスタンスで仕事をするようにしています」

今回クッションバックにループケアする服はお父さんの服だ。
「そうなんですが、いつ着ていたのかちゃんとは覚えていなくて。自分が小学校低学年の頃に着ていたんじゃないかな。でも、本当にかすかな記憶しかない。広島に引っ越して来てからはあまり着ていないと思います。着てないけど、物を捨てられない家なんですよね。昔のものも捨てないから、きれいなままで残っているものも多くて、その中の一つです。広島に里帰りした時にクローゼットを開けて、『これ持って帰っていい?』と言って東京で着ていました。だから、父が着なくなってから20代前半の僕が結構着たことになります。父は体が小さいので、僕にサイズが合うものは少ないんです。いいものをいっぱい持っているのにもったいない。だからこの服は数少ない父親から譲り受けたものなんです」
--自分らしく保つためのもう一つの仕事
山岸さんは、オペラ歌手以外にも実はもうひとつ仕事をしている。バンド時代から続けているビルメンテナンスの会社でのアルバイトだ。いまだに週2程度で続けている。続けなくては家計がままならない、というわけではない。続けていることには違う意味があるという。


「仕事をしてる間も劇のことを考えたり、役作りのこと考えたりしているんですが、あえて続けているところはすごくあります。eastern youthというバンドはご存じですか? 彼らもずっと職人を辞めなかったんですよね。よくライブに行っていたんですけど、職人を辞めずに音楽をやっているところがすごく好きで。ご飯を食べるための音楽ではなく、やりたい音楽だけをやるために、他の仕事をしながらインディーズであり続ける姿勢がすごくしっくりきていました。実際何年か音楽だけの生活をしたこともあるんですが、何かが違った」
そこで保たれるバランスが、山岸さんが純粋な気持ちとやり方のまま、地方でオペラを続けるために必要なことなのだろう。
「子どももいるので、音楽だけの生活になればやりたい仕事だけを選ぶというのは難しいかもしれません。ピュアな部分を自分の中で割りたくなかったというのはある。もちろん、効率は良くないけど、心身健全に生きていける気がしています」
--地方でオペラを仕事にするということ
地方でオペラを仕事にするというのは、なかなか当事者以外は想像がしにくい。全体のシーンも含めどうなっているのだろうか。

「地方でのオペラの起こりは、父のように中央で勉強した人がそれぞれ帰郷したところで生徒さんを募って、そこから団体、グループが出来上がったことによります。オペラ以前に各地方にオーケストラがあればそこと組み合う、またはそのために組織するなどして、そうしたところから自然な流れで集まりオペラが始まったのだと思います。どこかの地方が突出して盛り上がっているということはなくて、どこも淡々と続いていますね。皆さんがどんな世界か想像できないように、声楽の世界は閉じてるんですよ。異業種の人とのつながりをほとんど持っていない。だから、一度ズレるとそこはズレたままになってしまう。チケットを売る時も、お願いだから来て!みたいに必死で売るような」
オペラをおもしろそうと思って来てもらい、実際におもしろいと思ってもらう、思わせるという循環がないとなかなかオペラの世界が広がっていかないということ。

「この人にこんなに言われたら買うしかないわね、みたいな感じじゃだめなんですよ。イタリア語で歌うので字幕が出るのですが、字幕読みながら観てもよくわからなかったという声になってしまう。オペラってこういうもんよねという距離感を持たれ続けたまま何十年も来ているのが今です。それで賄えているという意味で危機感はあまりないのかもしれませんが、さすがにこのままではと思っています。言ってしまえば穴だらけなので、やろうと思ったらやることは死ぬほどあります」
26歳からオペラを始め、外の世界を見てきた山岸さんだからこそその危機感を覚えたのだろう。そしてオペラを愛するがゆえに、いろいろな人に楽しんでもらいたいという思いが強い。
「自分は舞台の本数をそれなりに体験してきて、日常がひっくり返るほど感動してきた。だからこんなもんじゃないはずというのがすごくあるんです。もっとたくさんの人の目に晒させてみたい。だから、僕はまだオペラに来たことがない人を呼ぶようにしてるんです。公演する演目の中身のことを説明して、『これ読んできて』とあらすじも渡し、稽古の様子も話しということまでやると、見に来てくれた人は、ほぼ100%リピーターになってくれます。手作りの感覚でもしっかり伝えれば伝わる。やればできるんだと」
そして、山岸さんはこれから新しいステップに挑もうとしている。
「近いうちに東京に出てオペラの仕事をしようと思っているんです。メイド・イン・広島でオペラを勉強してきて、西日本での仕事には割と手応えを感じているので、元々いた東京には友人も多いこともあって、自分のこれまでの成果とこれからの展望を見てもらえたらと思っています」
広島発のオペラが東京を始め、もっと広い世界で観られる未来が楽しみだ。


--山岸玲音さんのクッションバッグが完成しました
山岸玲音さんのお父さんのレザージャケットをループケアし、クッションバッグに仕立て直しました。


聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

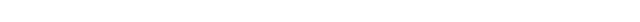

聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

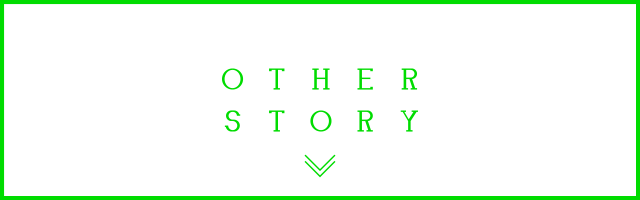
勝矢珠容子さんと
子どもの入学式で着た
絵羽織
株式会社勝矢和裁 会長
19.05.18

友村晋さんと
母親が作ってくれた
顔入りリコーダー袋
株式会社ミジンコ 代表取締役
19.04.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

川口朋子さんと
2回しか着ていない
着物
会社員
19.11.18

新里カオリさんと
母親が買ってくれた
ワンピース
立花テキスタイル研究所 代表取締役
19.08.09

梶原恭平さんと
半面教師の父親の
現場用作業着
広島経済レポート取締役
19.04.29

森田麻水美さんと
ウィリアム・モリスの
ファブリック
アートディレクター
19.09.08

沖眞理さんと
使って洗って変化した
エプロン
日常を楽しむ人
19.03.18

津金美奈さんと
自分で一式揃えた
成人式の着物
カフェ「kipfel.」店主
19.03.02

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18


勝矢珠容子さんと
子どもの入学式で着た
絵羽織
株式会社勝矢和裁 会長
19.05.18

友村晋さんと
母親が作ってくれた
顔入りリコーダー袋
株式会社ミジンコ 代表取締役
19.04.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

川口朋子さんと
2回しか着ていない
着物
会社員
19.11.18

新里カオリさんと
母親が買ってくれた
ワンピース
立花テキスタイル研究所 代表取締役
19.08.09

梶原恭平さんと
半面教師の父親の
現場用作業着
広島経済レポート取締役
19.04.29

森田麻水美さんと
ウィリアム・モリスの
ファブリック
アートディレクター
19.09.08

沖眞理さんと
使って洗って変化した
エプロン
日常を楽しむ人
19.03.18

津金美奈さんと
自分で一式揃えた
成人式の着物
カフェ「kipfel.」店主
19.03.02

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18
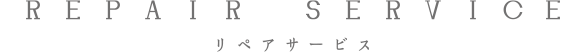
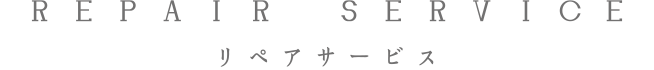
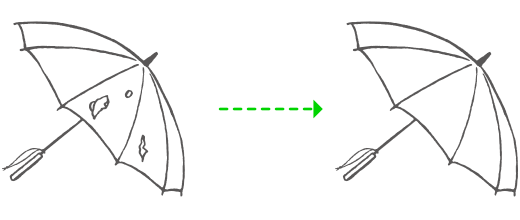
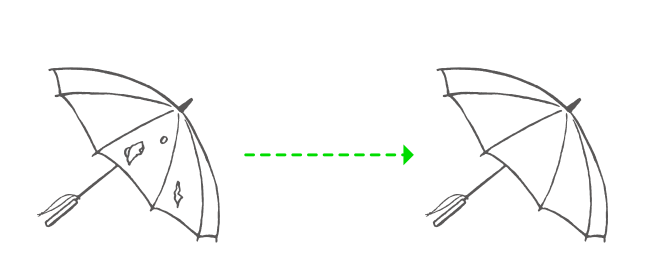
商品毎に、1回分の無料修繕サービス(リペア券)がご利用いただけます。
完成品といっしょにリペア券をお届けいたします。