
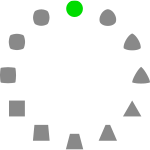

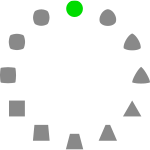


勝矢珠容子さん
と
子どもの入学式で着た
絵羽織
19.05.18
HIROSHIMA
1982年創業の勝矢和裁は、日本全国から着物の仕立てを依頼される非常に優れた職人の集団だ。会社を始めた勝矢珠容子さんも元々職人であり、いまなお手を動かしている。母親にもう辞めるとひとこと言えなかったことが、ここまで続き、日本の優れた文化を継承しつづけているという勝矢さんの着物と仕事。
--PTAルックとも呼ばれた黒羽織


会長の勝矢さんが日傘にループケアしたいと持ってきたのは、入学式や卒業式でほとんどの親が着ていたことからPTAルックとも呼ばれた黒羽織を仕立て直したコート。ループケアで仕立て直す前に、すでに一度ご自分でリメイクをされたものなのだ。
「40年以上前ですが、長男の小学校入学の式で着たものです。仕立て直したのは3年ぐらい前だったと思います。箪笥に納めていてもと思って、着物って仕立て直しがきくから、こういうコートにしたら着物の上にさらっと着れるかなと。というのも、お客さまがみんなこの黒羽織を持ってらっしゃって、どうしたらいいかよく聞かれて、じゃあ提案しようかと仕立て直してみたんです。本当は違う裏地が付いてたんだけど、私の他のコートの裏地を使って作り直しています。仕立て直した後は、結局一回も着てないんですが(笑)」

黒に五つ紋が正式の喪服。結婚式には留袖が最高の服装になり、コートを羽織ればちょっと崩した感じにも見え、略礼装のようにもなる。日傘となって、約40年ぶりに文字通りに日の目を浴びることになる。
「仕事柄着物はたくさんあって、でも普段は洋服なんです。式や行事ごとのようなフォーマルな場はいつも着物です。1947年生まれですから、子どもの頃の母は学校の参観日も着物を着ていましたね」
--お米もあったし、アメリカものもあって、恵まれた家庭だった

田んぼと山ばかりの広島県廿日市の山奥で生まれた勝矢さん。バスがたまに通るぐらいで、荷物を運ぶ馬車も通っていたような時代。田んぼは牛が耕していた。
「実家は兼業農家でした。農家だったせいか戦後も食べるものもないみたいなことはありませんでした。着るものは、モンペや絣、ネルのようなものを親が縫ったりして着ていましたね。でもみんな着たきりすずめ。みんなのズボンに継ぎが当たってたし、靴がないから草履を履いてくる人もいました」
みな等しく貧しい時代ではあったが、勝矢さんはロサンゼルスにいた祖父の姉からいろいろなものが送られてきてもいた。年に1、2回、着るものもたくさん入っていたし、チョコレート、ココアやメンソレータムのような、当時なかなか手に入らないものもそこにはあった。

「親が隠していましたね。子どもは、もらうと覚えちゃうから。でも隠れて食べてました(笑) 食べものも足りない時代にうちはお米もあったし、アメリカものもあって、恵まれた家庭だったと思う。しかも祖父が役場の助役をしていたので、現金も入り、田んぼもあった。アメリカの祖父の姉へのお返しを送りに、親と一緒にバスに乗って街に行き、味付けのりをいっぱい買って船便で送りましたよ。軽いから送料が安く済むんですよね」
--どうやって辞めようかばかり考えていた
高校を卒業する頃、これからは共働きで稼いでいけるように手に職をという母親の考えで、今の仕事になる和裁の仕事を始めることとなる。勝矢さん自身は短大に行くかなーくらいの考えで、自分の将来を具体的に考えてはいなかった。
「夏休みになったら突然着物を縫ってるとこへ連れていかれて、あんたはここで和裁を習ったらいいと言われて。よく分からないけど、そうなんかなと。それが今まで続いてるんです。当時、編み物が好きだったんですよ。母はそれを見て手先が器用なんじゃないかと考えて、この仕事を勧めたみたいです」

呉服屋さんが経営している専属の仕立て職人を育てる事業所で、住み込みでみんなと一緒に生活しながら、お仕事を教えてもらって、技術を覚えてということを繰り返して、1年たち、2年たち。入ったものの、毎日辞めて帰ろうと思う日々。5人いた同期は夏頃には全員いなくなっていた。4年ほどで一応終わりになり、試験を受けるのだが、その頃になるとみんなお見合いをして結婚していくのが当たり前。24歳までに結婚をしなかったら行き遅れといわれた時代だった。勝矢さんは23歳で結婚。親が探してきた相手とだった。
「どうやって辞めようかばかり考えていました。夏休みに家に帰ったとき、もう親に『辞める』の一言が言えなかったのが今まで続いている感じ。『お母ちゃんのためにしたげよるんよ、私』とか言ってみても、母は『いいよ、お母ちゃんのためにしてちょうだい』って。トボトボと戻っていきました。同期が全員いなくなって、私も辞めたかったけど辞めて何をするのかと考えても自分のしたいことがなかった。また1から修行も嫌だなと思って、ここでやるしかないんかなと思ってみたら、マイナス思考からプラス思考になって、苦手だった先輩がいい人に見えてたりして、そう思えるとかわいがってもらえるようになるんですよね」
--研究所の所長、そして独立へ

3年で卒業試験を受け、4年で教師の認定試験を受けた。4年目の終わりにお見合い結婚。その頃には、いつかは自分が先生になって教えてみたいと思い始めていた。夫にいつかは教室がしたいと話していたのだが、2人目の子どもが生まれた頃、突然その夢が実現することになる。
「習った所の先生と社長さんがうちに来られて、高齢だった先生の後継者になってくれないかと相談されたんです。下の子が生まれて2カ月ぐらいで、どうしようか悩んだとき、夫が『いつか自分で教室を持ちたいと言ってたんだから、これはチャンスかも分からん。受けてみたらどうか。協力はするから』と言ってくれた。給料は当時で10万円。家も与えてもらって、子どもも隣の床屋のおばあちゃんが面倒をみてくれるという、破格の条件でした」
夫は家業の米屋を長男と一緒にやっていたが、長男の娘婿が継ぐことになり、自由になった。辞めてどうするというとき、いよいよ自分たちで独立しようと考え、勝矢さんは教師として8年間お世話になった研究所を辞めることを決意。和服の需要が落ち込み、業界が厳しい時期でもあった。

「和裁研究所で所長として8年間お世話になったけれど、着物が売れなくなってもう呉服屋専属の仕立て屋が要らなくなった時代です。昭和57年です。2、3年前から、職人たちに十分に縫う仕事が与えられない状況で、縫って仕事を覚えるのにそのための材料となる仕事がない。専属だったからそこのお店の着物しか縫うことができず、手が空いてしまっていた。そうなると私がいる必要もないし、研究所も必要もないというので辞めたんです。働いていた子たちみんなが、私が辞めるんだったら付いていくと言ってくれて、専属はなくすからとみんなと一緒に辞めさせてもらい、一緒に独立しました。いちから人を探さなくても人がいたという意味ではラッキーといえばラッキー。あとは仕事さえあればいいから、そこからは営業をがんばりました」
あそこ行ったらいいよ、ここへ行きなさいという人の紹介を頼りに、縫った着物を持参し仕事を求めた。いくつものちいさな呉服屋さんの仕事を集めて、どうにかやりくりしていたが、仕事がない時期もあった。創業時にあった貯金もだんだんなくなっていった。
「どうなるんだろうという不安もいっぱいありました。同業者には、いまさら始めてばかじゃないかと言われたりもして、最後は夫婦で屋台でも引いて歩くぐらいの覚悟でやれと言われていました。当時、私は34歳、夫は36歳でした」
--夫とたてた3つの宣言


創業した日、勝矢和裁は3つの目標を立てスタッフに宣言をした。
「創業日の3月1日にみんなを集めて、まず『今日から勝矢和裁が始まる。みんな他人だけど、勝矢ファミリーで家族だ』と話し始め、1つ目の目標は『いつかはコンクールで日本一になろう』だと。全国から500人ほどが集まって技術を競い、50位までが入賞。1人連れて私が参加したら初回は50位にも入れませんでした。そこから、入賞者はどんなことをしているのか、いろんな講習会に行ったり、人が縫ってるものを見たりして必死に勉強し、次の年は4番になりました。そうしたら、広島の勝矢って誰だと注目されるようになった。それからは営業をしなくても、仕事が取れるようになって、その2年後にはついに1番に。それ以後は当たり前のように入賞をするようになって、いろんな大会の金メダルをもらいました。意地悪もされたけれど、そうやって技術レベルを高めることによってみんなに自信が付く。会社が有名になることよりも、最後には自分で独立していく仕事だし、金メダルをもらうのはその人で、会社に残せるものじゃない。もう一つの目標は、『自社で社屋を建てよう』ということ。4年経って、ちっちゃいながらも羽衣町に建てることができました。最後は、『10年経って勝矢和裁がまだあったら、みんなを招待して感謝の会を開く』という約束をしました。実際10年経って開催し、すべてを叶えた11年目の終わりに夫が亡くなりました」


47歳、有言実行を果たして旅立った。年末31日、風邪をひいたと言って病院に行き、年明けに肺がんの末期だと分かり、1ヶ月も経たないうちに亡くなった。バブルも終わりを見えた93年のことだった。
「いいことはめったにないですよね。大体、ピンチとチャンスは繰り返しやってくる。夫が亡くなった頃、それまで日本でしかなかった縫製の仕事を中国に発注することが増えてきたんです。でも取引先に、勝矢さんは国内も残ったほうがいいって。みんながみんな海外も出ていく中で必ず国内は必要になってくるんだから、どこか残らなきゃいけないと言われ、結局国内へ。今ではベトナムに工場があるんだけれど、当時海外の仕事が急激に伸びて、夫が亡くなって2年ぐらいで売り上げが約3倍になっていました」
--技術者と経営者
バブル期には2兆円と言われていた着物市場が今は2500億程度。そのうちの加工業はそこから10分の1。同業者も減っている。


「着物は日本の民族衣装だから、残るのは残るんと思うんです。でもどういう形で受け継いでいくかはきちっと考えなくちゃいけない。すごく狭くても、売り上げは落ちても、利益を確保できる仕組みをつくっていけば人がいない時代になっても可能性はある。うちは全部手作業でしょう。だから今いる人たちを大切にして、利益を確実に確保できるようにやり方を変えていくことを社長が今がんばってくれています。技術者だった私が社長のときとはまったく違って、現場でどうにでもなる、いいもん作ればええやろうみたいな話じゃない。いまの社長は完全に経営者ですから」
スタッフは毎年新卒で人が入ってくる。日本文化の技能伝承者になりたい、日本の文化を受け継いでいきたいという人がまだまだ若い人にも存在している。熟練の職人と仕事をともにし、仕事場を通じて技術が受け継がれていく。ひとつひとつの針目が正確に現れ、皺やピリつきがなくピタッと収まっているもの。パッと見た瞬間の仕上がりの良さに技術は現れる。




「社長からは、『皆さんは利益を考えなくていいから、お客さんのために何ができるか、どうやったら喜んでもらえるかだけを考えてください。あとはこっちで僕がやりますから』と言ってもらえています。だからみんなも、あ、これをやらなきゃとか、あれをしたらいけないとか、こうしたらもっと良くなるということを自分たちでよく考えてくれています。私は縫ったりはしてないけど、いろんな軽作業をしてます、人不足だから、現場の人として働いています。でもこの歳になっても技能の世界はできるんですよね、ずっと。今、一番年上の人が76歳なんですね。その人が一番こだわりのあるお客さんや三越さんとかを担当していて、絶大な信頼と評価をもらっているんですよ。若い人を育てるときには、お茶の出し方からいろんなことをその人が教えてくださる。駄目なものは駄目とはっきり言われて、成長していくんです」
お母さんの手に職をという思いから始まり、辞めると言えないままだいぶ遠いところまで続けてきた。
「会社はみんなのもので、私のものじゃない。その辺をしっかり話して、何のために働くのかをみんなで考え、会社が得た利益は給料としてみんなに返していく。だからみんなが頑張ればお給料も上がるんだよ。社長がいい思いするための仕事じゃないよって」
女の人の手に職として成り立ってきた世界ではあるが、決して女の人だけが着物を仕立てる人ではない。そのためにも確固とした技術と文化、そして収益が生まれるようにならなければいけない。上の世代の着物はまだまだ箪笥の中に眠っている。勝矢さんの着物が日傘になるように、みんなが幸せになるために着物の様々な可能性を勝矢さんたちはこれからも考え続けていくのだろう。

--勝矢珠容子さんの日傘が完成しました
勝矢珠容子さんの子どもの入学式で着た絵羽織をループケアし、日傘に仕立て直しました。

聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

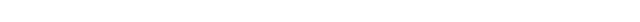

勝矢珠容子
株式会社勝矢和裁 会長
1947年広島生まれ
持ち前の手先の器用さから母親に和裁への道を勧められる。
高校卒業後、住み込みで和裁士としての修行を始める。
26歳の時、その腕を見込まれ指導する立場となり、多くの和裁士
を育てていく。
その後、独立し夫と共に株式会社勝矢和裁を立ち上げる
時代と共に変わりゆく和裁の世界であるが、日本の民族衣装を守り
継承していく役割も担う存在として活躍中である。
勝矢和裁
聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

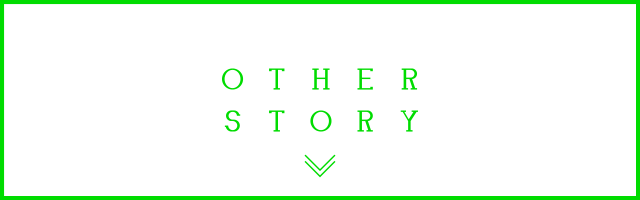
友村晋さんと
母親が作ってくれた
顔入りリコーダー袋
株式会社ミジンコ 代表取締役
19.04.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

戸川幸一郎さんと
描いて拭いて汚した
仕事着のパンツ
絵画造形家
18.12.08

新里カオリさんと
母親が買ってくれた
ワンピース
立花テキスタイル研究所 代表取締役
19.08.09

杉本拓史さんと
NZ遊学を共に過ごした
フリース
日本料理「野趣 拓」店主
19.02.05

梶原恭平さんと
半面教師の父親の
現場用作業着
広島経済レポート取締役
19.04.29

沖眞理さんと
使って洗って変化した
エプロン
日常を楽しむ人
19.03.18

津金美奈さんと
自分で一式揃えた
成人式の着物
カフェ「kipfel.」店主
19.03.02

藤島孝臣さんと
沖縄に溶け込むための
泡盛Tシャツ
ガラス工芸家
18.09.28

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18


友村晋さんと
母親が作ってくれた
顔入りリコーダー袋
株式会社ミジンコ 代表取締役
19.04.08

垣根千晶さんと
おばあちゃんの
着物
帽子デザイナー
18.12.29

戸川幸一郎さんと
描いて拭いて汚した
仕事着のパンツ
絵画造形家
18.12.08

新里カオリさんと
母親が買ってくれた
ワンピース
立花テキスタイル研究所 代表取締役
19.08.09

杉本拓史さんと
NZ遊学を共に過ごした
フリース
日本料理「野趣 拓」店主
19.02.05

梶原恭平さんと
半面教師の父親の
現場用作業着
広島経済レポート取締役
19.04.29

沖眞理さんと
使って洗って変化した
エプロン
日常を楽しむ人
19.03.18

津金美奈さんと
自分で一式揃えた
成人式の着物
カフェ「kipfel.」店主
19.03.02

藤島孝臣さんと
沖縄に溶け込むための
泡盛Tシャツ
ガラス工芸家
18.09.28

高亀理子さんと
ホホホ座尾道店の
エプロン
イベントプランナー&移動カフェ店主
19.01.18
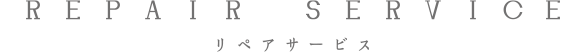
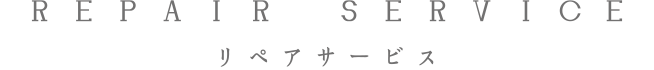
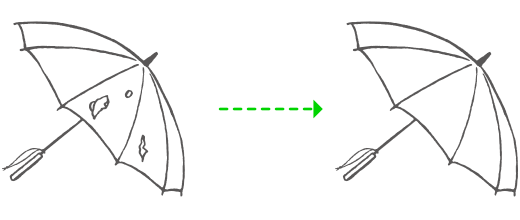
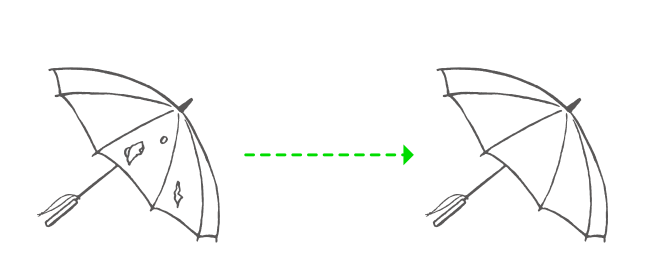
商品毎に、1回分の無料修繕サービス(リペア券)がご利用いただけます。
完成品といっしょにリペア券をお届けいたします。