
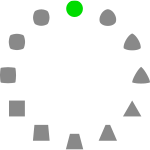

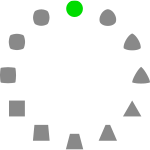


竹中庸子さん
と
三世代で受け継いだ
被布
18.06.18
HIROSHIMA
認知症の方を中心とした介護施設や地域のコミュニティスペースを運営する竹中庸子さんは、自身も進行性難聴というハンディを持ちながら、ひとりひとりの個性に合わせたケアをデザインし、その人の居場所を作っています。元々介護とは無縁の人生だったところから、自治体へのアドバイスをするまでになった竹中さんは、何を思い、人々をケアするのか。

--認知症=絶望的ではない
竹中さんが代表を務める特定非営利活動法人もちもちの木は、「土橋のおうち」「古田のおうち」「庚午のおうち」という3つの介護事業所と地域コミュニティ施設を運営している。若年性から高齢まで、さまざまな認知症の方が利用されている。

「ちょっと前の高齢者は、認知症イコール絶望的、みっともないという感覚でした。人の前に出られなくなり、黙って、どんどん悪くなる。認知症の症状で落ち込んで鬱になる人もいます。認知症が鬱になったらとても大変だけど、団塊の世代ぐらいの人たちから、認知症になってもオープンに活動する人が増えてきて、カミングアウトした人は、進行しにくいというのが言われはじめてきたんです。がんは命がなくなるかも知れないけど、認知症だけでは死ぬことはない。生きているけど、今までの自分とは一度お別れして、認知症の自分を認めた上でリカバリーしないといけないんです。」
日々何かを覚えてることが困難になっていく自分を正面から認めることは簡単ではないだろう。そうした状況に向き合うことに対して、竹中さんは耳が不自由になるという経験によって、気持ちが少しわかるようになったという。

「突発性難聴がきっかけで高い音から聞こえなくなってしまう進行性難聴になってしまって、静かな場所であればいいんですが、周囲に音がある中での会話はほぼ無理になってしまいました。障害者3級です。きちんと喋るようにいつも心掛けておかないと喋れなくなっちゃうんです。お昼なのにこんばんはと言ってしまったみたいな。脳の誤操作もあって、ちょっとした認知症のような状態。諦めて泣いた時期もあるし、車の運転も怖かったし、初めての人としゃべるのが嫌だった時期もある。だから認知症の人たちの気持ちが少しは分かるんです。今までの自分と違ったハンディを背負った痛さみたいな。」
--B型肝炎をきっかけに旦那さんが飛び込んだ福祉の世界
元々は主婦だった竹中さんの人生は、旦那さんが30代でB型肝炎になったことで徐々に変化していくことになる。旦那さんは会社を辞めて自宅療養となり、竹中さんが働くことに。仕事一筋でがんばってきた旦那さんは料理も何もできないまま家にいる生活。その頃から旦那さんの世間に対する見方が変わってきたという。2000年頃、旦那さんは友人の福祉の仕事を手伝い始める。
「B型肝炎とは7年ぐらい格闘していました。元々ラテン系の性格で、もう仕方がないみたいに諦めて色々やるようになって、料理もシフォンケーキ焼いて出せるぐらいまで楽しんでいました。そんな時、福祉の現場を見て、なんだこりゃと感じたようです。ジャズとワインとチーズが大好きだった自分が行きたいと思える場所がなかった。全然自由じゃないところばかりで、ケアは暮らしてる側にあるべきじゃんと考えて、自分でやってみようと、田舎の広いところではなく、狭くてもいいから町の真ん中で探し始めたんです。」


当事者になってみて初めてわかることがある。竹中さんが難聴をきっかけに認知症の方の気持ちがわかったように、旦那さんは自分らしさを抑えて過ごさなければ行けない場所に違和感を持った。しかし、いきなりそんな計画がうまくいくとは思えるはずもなく最初は反対していた。
「もちろん私は大反対でした。お金はないし、子どもが大学に行くときだったし。ただ、なんて言ったらいいか、やっぱりうちの家族の中ではパパが王様だったんですよ。」
呉服の会社で経理の事務や雇用管理をしていた竹中さんは、当然介護の現場とは無縁。経理やご飯を作るといったできる範囲で手伝い始めた。土橋のおうちには多様なバックグラウンドの人がいた。竹中さんは、“認知症の高齢者”というラベルで一括りにするのではなく、〇〇さんという個別のひとりとして向き合うことの必要性を実感していく。
「最初見た人が90歳の女性で、すごい人でした。借家の経営と株をしているおばあさんで半端じゃなかった。『私は頭がぼやけてしまって、自分を管理ができなくなったからあなたに管理してもらいたい』と言われたんです。株じゃなくて自分のことをですよ。その人は自分でその決断をできるほど自立してたんですね。そういう人がいるんだなと驚きました。他にも経営者だった人が多かった。お年寄りは田舎が好き、土いじりが好きみたいな先入観を持っていたので、『じゃあ、今度土いじりしようかね』と言ったら、『汚い。そんなものは触りたくもない』って怒られて、どうしようと話してたら、マニキュアをするとか、喫茶店でコーヒー飲むとか、そういうスタイルの人たちだったわけです。そこで初めて、固定概念が打ち砕かれました。私たちが思ってた“一般的”なお年寄り、高齢者っていうのじゃなくて、それぞれみんな違うんだってこと。だから、認知症の人、高齢者とまとめるのではなく、○○さんというひとりひとりのスタイルでずっと付き合ってきました。」
--旦那さんの死と鍛えられていた仕事力

仕事をしながら手伝いをしていたが、2008年に旦那さんが亡くなる。亡くなるまでの二年半は癌との闘病生活。癌とわかったときは、そんな短い期間があるのかと思うが、あと二週間と言われたそうだ。ところが、奇跡的に抗がん剤が効果を発揮し、そこから一年半、死を見据えた旦那さんの生活がはじまった。
「事前に保険も出るので、保険を全部使いたい放題する楽しい生活をして、寄付したり全部使って亡くなりました。もう、あれ以上生きてたら赤字だった(笑)。今、ちょっと笑い話ですけど、全部使ってそれでよかったと思います。50日間入院していた間は毎日通って、病院でシャワーを浴びて、一緒にご飯を食べて、寝て、起きたら行ってきますと仕事行ってという日々。泣いてましたよね、一体どうしたらいいのって。夫は仕方ないだろって言うわけ。ワンマンだったので、なんか私が言ったら、「はいって言えばなんでもこの世はうまく行くんだ」っていうふうに私に教えるわけ、うちの夫は。「おまえは、はいって言ってればいい」って言ってたから、めんどくさいから、はいって。意外と、はいって言ってやってたから、あんまり大変じゃなかったです。」

本当に家庭内では王様だったようだ。旦那さんが亡くなって今年で10年、「はい」とうなずきながら従ってきたが、その期間で竹中さんは「意外と鍛えられていた」。亡くなってから、土橋のおうち以外に、ふたつのコミュニティ施設をつくった。
「夫が喜ぶだろうなと思って、弔い合戦みたいな感じでした。開設者の意を引き継がないといけないみたいな感じもあったし、みんなエネルギーがあるというか。残してくれたお金もあったので、今ならできると思って、古田のおうちをつくりました。それが、介護事業とコミュニティスペースを合わせた新しい形のスペースとして注目を浴びたんです。大変なことはあったんですけど、意外と鍛えられていた。育てられたというのか、なんか分からんけど。困らなかったことは確かです。仕事ではね。プライベートは大変でした。20年間ごみを捨てる係じゃなかったから、急にはゴミを捨てられないですよ(笑)。」
それくらいのことと思うのは簡単だけれど、それは単純作業ができないということではなく、旦那さんがいなくなったということの象徴として、やっていた役割を安易に切り替えられなかったということだろう。
「半年はロス現象が大変でした。でも仕事が来るんですよ。どんなときでも、どんな状態でも仕事はトレーニングされてきたから、できた。帰ってからが大変でしたね。すっごい太りました。10キロぐらい太った。泣いて、ずっと食べ続けていました。」
--年寄りだけを集めるな。多世代だからこそ機能する。



コミュニティ施設の運営は簡単ではなかった。集いの場にお金を落とすという感覚は近隣住人にはない。場所貸しという形で維持することにしたが十分ではなく、募金活動や寄付を募るなど苦労は多かった。本業である介護事業への圧迫もあった。それでも竹中さんの、やっぱり私はこれをやるんだという気持ちに変わりはなかった。
「やっぱりこれが私の役割なんだって感じです。お金を稼ぐとかじゃない。お金もうなくなるばっかり。これ誰がやるの? 私がやることなんだって。今では迷いはないです。良いことも悪いこともそんなもんかみたいな感じ。」
古田のおうちともうひとつのコミュニティスペースである庚午のおうちには、シェアハウスの機能もある。そこには学生からご高齢の方まで、多世代に渡る住人がいるそうだ。これは珍しいケースなのではないか。
「社会は多世代じゃないと成り立たない。なのに、どこも年齢別でしかない。だから息苦しいし、風通しが悪い。介護をやってたら、高齢者だけって絶対に成り立たないんですよ。高齢者だけを集めるから手がかかるんです。施設に赤ちゃんが1人来ただけで、介護職いなくていいぐらい楽しく、明るくなります。例えば、死にそうなおじいさんがいて、人生どうでもいいんじゃないとか言われたら、もうどうでもいいかなみたいな抜け感は、偏った世代編成では同質化していって成り立たないんです。高齢者専用賃貸住宅がいっぱいありますけど、年寄りいっぱい集めて協力して暮らすなんて、手がかかって大変なだけだよね。」
古田のおうちでは、多世代寺子屋ネットワークを作った。今では中学生が町づくりをするようになってきた。50年後は君たちが中心の時代だから君たちで考えようと、二ヶ月に一度中学生自身が企画し100人集まることもあるまでに成長した。
--受け継ぐ被布と洋裁師の母の思い

今回ループケアするのは、竹中さんが子どもの頃に着ていた被布。七五三の時、三歳の子が着る着物だ。受け継ぎ、着続けてきた服。被布は隣のおばあちゃんが作ってくれたものだが、普段着ていた服は、洋裁師だったお母さんが作ってくれていた。
「隣の家に和裁のできるおばあちゃんがいて、作ったんです。おばあちゃんの孫が男の子ばかりだからって喜んで作ってくれたそうです。私の娘も孫の女の子2人も着ました。他にもいろいろ探したんですよ。私が子どもの頃に着ていたスイスレースのワンピースがどんどん解体されて、孫のスカートになっているのもありました。靴も服に合わせて塗り直したりしていましたし、私のウェディングドレスも作ってくれました。」


「子どものころからずっと母が作った服を着ていて、中学校3年で初めて服を買いました。それもあってか物心付いたら日常的に鉛筆で絵を描いて、こんなん作ってと生地屋に行って生地を選んで、帰りにボタン屋に行くみたいなルートでした。分からなかった。みんな買ってるって。母親は楽しかったみたいで、ご飯を作るより服を作りたかったみたい。多分、それをやって仕事がしたかったんだと思いますけど。」
竹中さんのお母さんは、早い時期からBSに加入し、パリやミラノのコレクションを全部観ていたそうだ。テレビで観たクリスチャン・ディオールのデザインを真似してスカートとコートを作ってくれたりというのもよくあった。
「でもそれって母にとっては実験なんです。観たものをそのままパターンに起こしてしていくのが楽しかったのね。だから、気になったらずっと同じ形を作るんです。生地のカットや方向を変えて試したりしながら。5枚もあってどうするのこれ、みたいな服もありました(笑)。服作りを教えて仕事にすればよかったと思ったんですけど、職人だからめんどくさくて人に教えられない人でした。」
お母さんが子どもたちの服をすべて作っていたことについて、広島で生きてきた人ゆえの理由があった。
「母は19歳の時、原爆にあっているんですね。ガラスが体にたくさん刺さってしまったりして、もう結婚はできないと思って、洋裁で身を立てるしかないとおばあさんがすぐにミシンを買ってくれたそうなんです。その母は、2016年の10月に急死しました。亡くなる前日、うちの娘とロールキャベツを山のように作って眠った次の日の朝、亡くなっていました。父は98で健在なんですが、父の枕元でバタンて。母は亡くなったのに母が仕込んでいたパンが、パン焼き機で焼けている朝。テーブルにはカボチャのスープを作ろうと思って材料のタマネギとカボチャが置いてありました。明日やることまで用意して逝った。だから、まあいい亡くなり方だったのかな。89歳でしたけど、最後まで自分の服は全部作ってました。」

被布は今回アルバムになるわけだが、これまでの写真は旦那さんが亡くなった時、自分ではできないと子どもたちに遺品整理を頼んだところ、思い切りよく相当数を捨てられてしまったそうで、何が入るのだろうか。
--竹中庸子さんのアルバムが完成しました
竹中庸子さんの三世代で受け継いだ被布をループケアし、アルバムに仕立て直しました。

聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

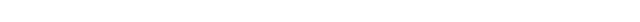

竹中庸子
特定非営利活動法人もちもちの木理事長
介護福祉士・認知症ケア専門士。1990年より社会福祉法人の設立や特別養護老人ホームの開設にかかわる。
1992年にボランティア団体レジャンティアを結成。その後、特別養護老人ホームの開設ボランティアを経て、2001年「NPO法人もちもちの木」を設立。認知症の方の暮らしを支える活動を開始。
共に活動してきた夫がガンになり、3年余りの闘病生活ののち、在宅にて看取る。20歳時の突発性難聴をきっかけに進行性の感音性聴覚障がい者。
現在は介護事業を展開しつつ、多世代のつながりの希薄が社会課題と捉え地域の様々な人の一生をつないで支えるコミュニティーワーカーとして活動している。
又、認知症サポーター養成講座の講師として、企業や学校などで講演を行っている。
聞き手: 山口博之
写真: 山田泰一

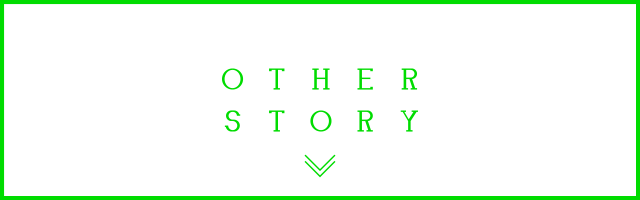
三浦剛さんと
人生を変えたハワイの
アロハシャツ
Garden creator
18.02.08

今津正彦さんと
苦しかった時代の
奥さんのワンピース
株式会社アイ・エム・シー ユナイテッド 代表取締役
18.06.28

佐藤恵子さんと
あの頃一目惚れした
スカート
整理収納アドバイザー/親・子の片付けインストラクター
18.07.08

堤信子さんと
好きになり始めた頃の
アンティーク着物
フリーアナウンサー/エッセイスト
18.03.28

山本美直さんと
子を通して繋がる母の
ツーピース
ブランド「ヒトツトテ。」作家
18.06.08

嵜本晋輔さんと
ガンバ大阪3年目の
ユニフォーム
株式会社SOU 代表取締役社長
18.04.18

池田沙織さんと
ふたりの子どもが着た
手作りの産着
アクセサリーデザイナー
18.05.28

浅野史瑠さんと
デザインした文化祭の
Tシャツ
雑貨作家
18.05.18

田村幸士さんと
父親からもらった
楽屋着の浴衣
俳優
18.02.18

藤江潤士さんと
サラリーマン時代の
オーダースーツ
シンガーソングライター
18.05.08


三浦剛さんと
人生を変えたハワイの
アロハシャツ
Garden creator
18.02.08

今津正彦さんと
苦しかった時代の
奥さんのワンピース
株式会社アイ・エム・シー ユナイテッド 代表取締役
18.06.28

佐藤恵子さんと
あの頃一目惚れした
スカート
整理収納アドバイザー/親・子の片付けインストラクター
18.07.08

堤信子さんと
好きになり始めた頃の
アンティーク着物
フリーアナウンサー/エッセイスト
18.03.28

山本美直さんと
子を通して繋がる母の
ツーピース
ブランド「ヒトツトテ。」作家
18.06.08

嵜本晋輔さんと
ガンバ大阪3年目の
ユニフォーム
株式会社SOU 代表取締役社長
18.04.18

池田沙織さんと
ふたりの子どもが着た
手作りの産着
アクセサリーデザイナー
18.05.28

浅野史瑠さんと
デザインした文化祭の
Tシャツ
雑貨作家
18.05.18

田村幸士さんと
父親からもらった
楽屋着の浴衣
俳優
18.02.18

藤江潤士さんと
サラリーマン時代の
オーダースーツ
シンガーソングライター
18.05.08
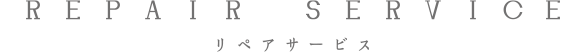
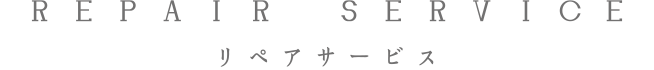
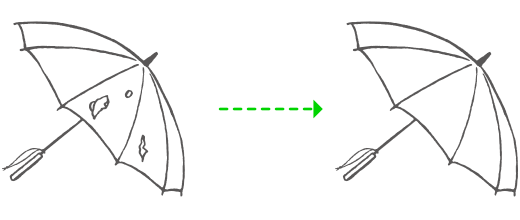
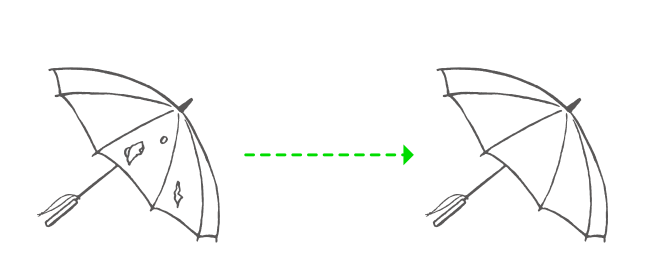
商品毎に、1回分の無料修繕サービス(リペア券)がご利用いただけます。
完成品といっしょにリペア券をお届けいたします。